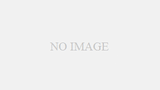「お茶といえば静岡」——多くの人がそう思い浮かべますが、2024年の生産量1位は鹿児島県。どうして勢力図が変わったのか?そして静岡はこのまま終わるのか?“お茶好きの視点”で楽しく深掘りしていきます。

ランキング(2024年の大きな流れ)

- 1位:鹿児島県(堂々トップ)
- 2位:静岡県
- 3位以降:三重、宮崎、京都などが上位常連
※年ごとに細かな順位は前後しますが、近年はこの顔ぶれが中心です。
2024年お茶の農林水産統計
関連記事:2024年の日本茶生産量 都道府県別ランキングはどうなる?日本一は静岡県?! 鹿児島県?(※この記事は、碾茶が荒茶にカウントされるとは知らず、予想が外れています)
関連記事:お茶の種類 一覧 お茶の全てがわかる!全28種 わかりやすく、詳しく解説
逆転の鍵は「抹茶(碾茶)」にあった

1) もともと底力はあった鹿児島
- 機械化が早い:乗用型摘採機の普及率が高く、大面積を効率よく摘採。
- 温暖な気候:生育が早く、四番茶・秋冬番茶まで狙える年も。
- 大規模化しやすい地勢:フラットな茶園が多く、導入・拡張がしやすい。
この「生産性の高さ」に、ここ数年**“追い風”が吹きました。**
2) 世界的な抹茶ブームで“碾茶”が主役に
- 抹茶=碾茶を挽いた粉。需要の伸びとともに、碾茶工場が続々新設・増設。
- 鹿児島は碾茶の生産量でもトップクラスに。
- さらに注目は簡易碾茶(もが)。抹茶向け原料の準備段階・代替原料として生産が急伸しています。
※簡易碾茶とは? 碾茶製造に必要な碾茶炉を使用せず、既存の煎茶生産ラインを使って碾茶に模して茶葉を蒸して揉まずに乾燥させたもの。主にラテ用、製菓用抹茶の原料として使われる。 熊本産 moga 抹茶 100g 簡易碾茶使用 農薬・化学肥料不使用(無農薬)
熊本産 moga 抹茶 100g 簡易碾茶使用 農薬・化学肥料不使用(無農薬)
楽天販売ページ・ヤフーショッピング販売ページ
3) 収量インパクトが大きい

- **碾茶・簡易碾茶は“葉を大きく育ててから摘む”**のが基本。
- 結果、煎茶より収量が数割〜最大2倍前後アップすることも。
- 収量×機械化×温暖地という「三拍子」で、鹿児島の生産量は一気に存在感を高めました。
※碾茶とは?抹茶を挽く前の原料茶葉で、揉まずに乾燥させたもの。
関連記事:2023年抹茶の原料である碾茶(てん茶)生産量1位は、鹿児島県。2024年はさらに急拡大の見込み
関連記事:抹茶の原料である碾茶は、このようにしてつくられる!
「碾茶工場が爆増」の現場感
- 抹茶需要の伸び=安定した仕向け先があるという安心感。
- 設備投資→処理能力アップ→一気に“量”を取りにいける体制が整う。
- さらに**簡易碾茶(もが)**の普及で、原料サイドの選択肢が広がったのも大きいポイント。
- 農水省他、補助金を出して煎茶から碾茶転換を支援
- 鹿児島県民は、昔から海外交易が得意。一致団結力があり、団結して一斉に進む傾向がある。
今後も鹿児島の1位は続くの?
**“抹茶ブームが続く限り、優位は堅い”**という見方が有力です。
- 海外の健康志向・和食人気・カフェ文化の拡大で、抹茶は“飲む”だけでなく“食べる”方向にも拡大(スイーツ、プロテイン、ベーカリーなど)。
- 需要に対して、鹿児島は“量を出せる設計”。この強みは一朝一夕では崩れません。
では静岡の復権は?「最大産地」から「最強ブランド」へ
量で真っ向勝負をするより、価値づくりで“復権”を狙うのが静岡の得意分野。
1) 首都圏近接 × インバウンド
- 東京からのアクセスが良好。体験・観光・学びを絡めた茶ツーリズムに最適。
- 工場見学、製茶体験、茶室体験、テロワール巡り…“行けるお茶”は静岡の強み。
2) 文化的資産 × 物語性
- 歴史ある産地・銘柄・作り手のストーリー。
- 単一園(シングルオリジン)や品種違いの飲み比べなど、“通好み”の世界観を磨ける。
3) 高付加価値の設計
- 深蒸し煎茶の洗練、希少ロット、手摘み、特蒸し・浅蒸しの多様性など、**“味の幅と技術の深さ”**は静岡の真骨頂。
- ペアリング提案(和菓子・チーズ・チョコ・発酵食)や焙煎違いの表現で、単価の最大化が可能。
- 海外富裕層向けの**“茶のソムリエ的”体験**は、静岡だからこそ説得力がある。
結論:静岡は“最大の生産地”ではなく、**“最も訪れたい・学びたい・語りたいお茶の聖地”**として価値を高めていく道が強い。
まとめ:産地の勝ち筋はそれぞれ違う
- 鹿児島:機械化・温暖地・碾茶&簡易碾茶の伸び=量×スピードの覇者。
- 静岡:首都圏近接・文化的資産・体験設計=価値×体験の王道。
抹茶ブームが続く限り1位は鹿児島優勢。ただし、“お茶の魅力を深掘りして世界に届ける”という意味では、静岡の復権(=ブランド再定義と高付加価値化)は十分にありえます。量か、価値か。——日本茶の面白さは、産地ごとに“勝ち筋”が違うところにあります。
おまけ:用語ミニ解説
- 碾茶(てんちゃ):抹茶の原料。被覆栽培で旨味を引き出し、揉まずに乾燥した葉を“挽いて”抹茶に。
- 簡易碾茶(もが):製造工程を簡略化した碾茶風の原料。需要拡大で生産が急伸。
- 深蒸し:蒸し時間を長くして濃厚な抽出とまろやかさを出す製法。静岡の代名詞的スタイル。

 熊本産 moga 抹茶 100g 簡易碾茶使用 農薬・化学肥料不使用(無農薬)
熊本産 moga 抹茶 100g 簡易碾茶使用 農薬・化学肥料不使用(無農薬)